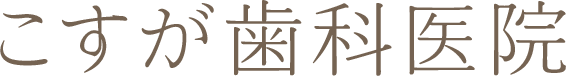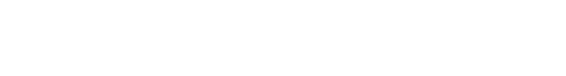科学的な目線で理念を思考する取り組み
SCIENCE OF PHILOSOPHY
歯科界の概念や症例についてなどを科学的に思考した事例を紹介いたします。臨床の世界でよく目にする報告や概念、解釈をさまざまな視点から科学し、次の展開への発展を目指し、掲載しております。日々患者様に真摯に向き合い、基礎に忠実な高い技術の治療を行う一方で、知識や経験を通して、根本的な概念や解釈を科学し日々研究を行い、発表、論文展開してまいります。
理念を科学する
その1
歯科界の一つの概念の紹介です。例えば補綴を行う際、シンメトリーに配列を行う事が大事とされています。
この概念を私達は一切否定する意思はありません。むしろ尊重すべきという立場です。では、この概念は言うなれば必要な要素なのか、十分な要素なのかと科学したくなる訳です。
2019年に発表を行いその後論文化する予定ですが、口腔内の私達が学ぶ真ん中と、体の真ん中を来院される患者で調べ直しました。すると、誰一人一致する方はおられませんでした。この瞬間、シンメトリーに並べるという概念は、その性格が変わります。シンメトリーに並べる規格なり基準が無ければその成立は意味を持たない可能性がある。あるいは、そもそもシンメトリーに並べる必要性などない。あくまでも論理をすすめる上での命題としてですが、どちらも成立する可能性が出てきます。
この命題に対し、何らかの論理展開を捉え補綴を行わないと時に、著しい問題を肉体に与える可能性が出て来る気がいたします。実際、そんな症例はゴマンとあるよう感じます。「理念を科学したい」のご紹介でした。
その2
歯科治療を行った後に「肉体」に症状を呈すようになった。
このような報告は臨床の世界では幾度か目にします。歯科で生きる私どもにとって一番嫌な報告は、歯科治療後「身体に痛みを覚える病気」に罹患したという報告です。歯科はその治療後に肉体症状を呈す場合、不定愁訴と扱います。これら表現に対し科学する事も可能ですが、今回は別の視点で科学をしたく思います。
例えば線維筋痛症では「器質性障害疾患であるがその器質性障害部位が不明という」結論を出しております。他方、歯科は「器質性障害は解決しているが機能性障害が起きている」という立ち位置というのが私達の理解です。器質性障害とは、どこかが破損・損傷を受けている状態を指し示します。疼痛性障害という視点で見ると、どちらもあたかも中枢神経感作が起きている状況に類似していると感じます。
そこで、これを科学してみたくなり、本年この具体的部位に関し発表を行い、その後、論文展開を行う予定です。壊れている場所が可能性としてでも明示できれば、次の展開が生まれると信じます。それが生命科学の下で働く仕事を選んだ側の責任と受け止めております。
その3
器質性障害や中枢性感作をご紹介しました。時に歯科は機能性障害という捉え方をしております。
この解釈が生まれた根底を科学するのも悪くないと考えております。科学というのは修正を繰り返しながら体系化を図るそんな性格を持ち合わせています。
中枢性感作という表現を咬合という世界に置換すると、例えば咀嚼パターンの乱れという具体表現になります。この意味は制御プログラムがおかしくなる、例えるならばマルチコアシステムにバグが生じ、本来の消費電量や発熱に異常を来し、複数の処理が同時進行に出来にくくなる。
治療による咬合環境が中枢性の影響を渡す結果を招く事があり得るならば、逆に中枢性に働きかける力が穏やかに身体の回復が図れるような咬合条件を科学できないか。人と言え動物である私達も回復を図る時にその回復が阻害される事、これが問題と考えております。
そこで、中枢神経感作の領域まで拡げて機能面の条件までを科学できないか?この一つの目標を達成するため、治療体系の転換を今現在取り組んでおり、科学の土俵に治療を乗せる事が大切だと考えています。