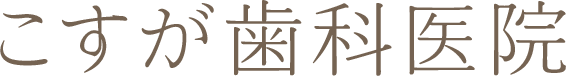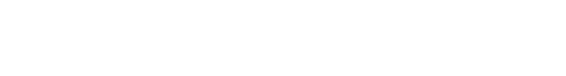歯科としての考えをわかりやすく掲載
TASKS
歯科医院を運営し、さまざまな治療をしていく中での課題や盲点を掲載しております。数多ある歯科医院ですが、当然ながら医院によってポリシーや治療方法などが異なります。その上で、自身の経験や歯科の歴史などの積み重ねをもとに、歯科医として科学的な目線からの考えを提示いたします。患者様との情報の共有を目指し、掲載していますので、お時間がある時にぜひお読みください。
歯科の課題・盲点
歯科治療を行うにあたり、当然ながら歯科の歴史の積み重ねからエビデンスに沿った情報に重きを置いて治療に取り組みます。
視点を科学に変えます。科学は「体系化された知識や経験の総称」ですが、ここを更に細分化した捉え方をご紹介いたします。
原因と結果という視点に立つと言葉の表現が変わります。「因果関係を探して行くのが科学的方法」。対して科学は「どの様な条件で何が起こるか記録していく中で、因果関係を分析する事」になります。言わば因果関係を立証しようとするのが科学です。
因果関係を示す重要な情報が得られて説明が出来るならば科学的と言い換える事が許されます。
論理的な展開を図る所まで原因と結果を説明できれば、科学的と評価が渡されます。
では、患者になる「あなた」に問い掛けます。
その受けた説明が科学的でも、科学でも構いません。どれだけ科学を意識した治療を紹介されたでしょうか?
ここに歯科の課題や盲点があるのではないかと個人的には捉えております。
科学にどれだけ正直に向き合えるか。このスタンスを治療では大事にします。同時に、臨床で避けなければならないと肝に銘じているのが「科学的説得力がある方向に誘導しない」という事です。臨床ですから、間違いや勘違いを患者に渡す事はしてはいけません。が、これが難しい。
科学は、常に誤りに修正を加えながら真実に近づくという側面があります。口腔疾患の全てに解決法や解放がある訳ではありません。
平たく言えば、分からない口腔疾患があっても不思議ではない。例えば痛みを伴う疾患に関しては解明不足の課題があると捉えるべきかもしれません。
科学の中にはパラダイム論と、従来の考え方を覆す捉え方があります。先に、情報という捉え方をご紹介しました。痛みの捉え方は「侵害受容性疼痛」「神経障害性疼痛」「痛覚変調性疼痛」と大学で学んだ実際と違う情報が既に出ています。
この視点に立つ時、実は新しい取り組み方が要求されると私どもは考えます。歯科の課題や盲点がパラダイムに表われるといった所でしょうか?
3つの疼痛分類を知り、大学で学んだ知識と比較を臨床医の端くれとして関連を調べます。
医科の場合、彼らの従前の捉え方では成立しない現症が出て来る際「関連図」という方法で分かっている事と分かっていない事を整理する手法があるようです。
知らぬ世界とはいえ「疼痛」に対峙するため、20年以上関連化を試みます。
生体反応により生じる性格を持っています。ならば、逆の生体反応を用いて痛みの軽減や消失を試せるのではないかと、パラダイムした発想が生まれます。科学でいう所の反証を試みるといった所でしょうか?
私どもは、学会で科学という土俵に研究が乗る事を期待し情報の発信を続けております。
歯科の課題や盲点が、まずは公にならなければ何も始まらないと考えるからです。
原因不明とされる疼痛が存在するならば、それに対し歯科界が対峙しなければ患者利益に反すると考えています。